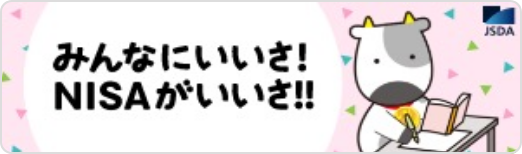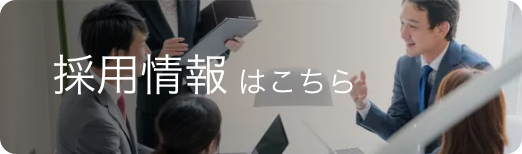投資について
- 株には「怖い」イメージがありますが、初心者でもはじめられますか?
- はい、始められます。お客様のご意向と投資目的、実情に合わせた対応をさせていただきますので安心してご相談ください。
- なぜ資産形成には投資が向いているのでしょうか?
- 現在のような低金利時代においては貯蓄(貯金)による利息収入があまり望めません。株式や投資信託への投資は、資本市場にお金を置く事で、資本市場の成長に寄与し、その成長に合わせご自身の資産が増える事が期待できます。
- 初心者が投資をするときには、どのような点に注意すればいいですか?
-
金融商品により、運用方法やリスクは異なります。投資を希望される商品の説明をお聞きになり、許容可能なリスクであるかを理解したうえで投資をすると良いでしょう。特に、これから投資を始めるに当たっては、長期投資・継続投資・分散投資を意識した投資信託などで運用すると短期的な価格の変動に捉われない投資ができます。営業社員へお気軽にご相談ください。
- 投資のリスクについて教えてください。
-
投資で得られる成果(=リターン)は定まっておらず、収益が大きくなる場合もあれば、損失を出す場合もあります。投資では、「リターンの不確実性(上がり下がりの変動幅)」をリスクと呼びます。一般的なリスクには、価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク(取引先が破綻して契約が履行されずに損失を被るリスクなど)・カントリーリスク(その国の政治・経済の動静により金利の変動や流動性を生むリスク)があります。
- どんな投資が自分に合うのかわかりません。
-
お客様の投資目的、投資経験のある・なし、運用資金、ご自身の性格や志向などにより、投資スタイルは様々です。まずはお客様のご意向を確認して最適なアドバイスをさせて頂きますので、営業社員へお気軽にご相談ください。
- 投資は売買や取引のタイミングが難しそうですが…。
- 株式や投資信託の売り買いで利益を上げようとすると、価格の値動きにより売買のタイミングの見極めは難しくなります。資産形成には中長期に投資する事が重要です。例えば株式であれば高配当や株主優待のある銘柄を中長期で保有するとか、投資信託であれば毎月一定額を積み立てる形にすると、価格変動によるタイミングをあまり気にせずに投資する事ができます。
- 投資を始めるのは早ければ早いほど良いのでしょうか?
- 毎月一定額を投資する「積立投信」などは、少しの金額からでも早く始める方がより良い成果が見込めます。
株式や投資信託を新たに買い付けて投資を始める場合は、まずは割高感のない銘柄を少額から購入するのが得策です。
- 預金貯蓄と投資に充てる金額の比率はどれくらいが長期的に見て良いのでしょうか?
- 家計の収入・支出の状況により様々です。月々に余ったお金を投資に回そうと思ってもなかなか余りません。まずは最低限必要な支出をしっかり見極めた上で、それを超える収入部分を貯蓄と投資に割り当てる発想が有効です。
貯蓄は緊急時に必要と想定される出費の範囲を目途にして、それ以外を投資に振り向ける事をお勧めします。
金融商品について
- 無理のない投資を始めたいのですが、数万円から始められる金融商品はありますか?
-
はい、ございます。少額から投資できる商品としては、投資信託を1万円から千円単位で購入できる「積立投信」があります。この中には少額非課税制度である「NISA(つみたて投資枠)」で購入可能な商品もあります。また、株式は100株単位での取引になりますので、株価が千円未満であれば数万円から購入が可能です。その他個人向け国債も1万円から購入できます。
- 投資信託に興味があります。通常の株の売買とどのような違いがあるのでしょうか?
-
株式は東京証券取引所等に上場している企業(銘柄)を100株単位で売買する事ができます。投資信託はお客様のニーズに合わせ、当社が優良な商品を厳選してご提案させて頂きます。商品により最低購入金額などが異なりますので、営業社員にお気軽にご相談ください。
- 積立投信と、NISAのつみたて投資の違いを教えてください。
-
積立投信は、毎月定時定額で買付できる投資信託の商品の事です。当社では1万円以上1000円単位の金額で毎月12日に買付する商品を60銘柄超、取り扱っています。
NISAのつみたて投資(つみたて投資枠)は、積立投信の銘柄の中から買付手数料が無料などの条件をクリアした商品だけを買付できる制度で、売却時の利益は非課税となります(通常は売却時の利益の20%が譲渡益税として課税されます)。当社では10銘柄ほどの商品がNISA(つみたて投資枠)で買付可能です。
- 資産が減るのは避けたいと考えています。元本が保証される金融商品はありますか?
-
日本国が発行する国債(個人向け国債を含む)であれば満期(償還)まで保有する事により、日本国が破綻しない限り元本は償還されますので、ほとんど元本割れするリスクはありません。
- どの株を選ぶか迷ってしまいます。株を選ぶコツを教えてください。
- 専門家の判断や市場の見極めなど、株式の選択基準を考えだすとキリがありません。最初は難しく考えずに、お客様の身近な企業や応援したい企業の株式を、消費者視点で選んでみるのもひとつの方法です。
- 株主優待について教えてください。優待を受けるための条件はありますか?
-
お目当ての会社から配当や株主優待を受けるためには、「権利確定日」(通常は各企業の決算期末)の2営業日前(「権利付最終日」)までに買付することが条件となります。
- 「日経平均株価」「トピックス」とは何を表しているのですか?自分が投資した株の価格と、どのような関係があるのでしょうか?
-
両指数とも上場銘柄全体の値動きを表す指数です。株式市場全体が上がったか下がったかを見る物差しと考えれば理解しやすいでしょう。「日経平均株価」とは東証上場の銘柄から選ばれた225銘柄の平均株価(株価の合計÷一定の定数)を表し、「トピックス」とは東証一部銘柄全体の時価総額加重平均(構成銘柄の時価総額の合計÷ある一定時点の時価総額)で算定されます。その為、「日経平均株価」は値段の高い(値がさ株)の価格変動に影響されやすく「トピックス」は時価総額の大きい銘柄の価格変動に影響されやすいという違いがあります。株式投資を行う場合、個別銘柄の値動きを把握することは重要ですが、同時に投資判断の目安として、マーケット全体の動きや方向性を把握する観点から両指数の変動を見ていく事は重要な視点になります。
NISAについて
- NISAとはどのような制度ですか?
-
株式・投資信託の売買の利益や、配当・分配金などの収益に対して、通常の証券税制上はその20%が譲渡益税や配当課税として徴収されます。この利益や収益が非課税となるのが、NISA(少額投資非課税制度)です。
尚、NISA口座は毎年1つの金融機関でしか開設ができませんので注意が必要です。
- NISAには2つの非課税上限金額(枠)があると聞いたのですが、どういうものでしょうか?
-
NISAに「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類があり、それぞれに年間の利用上限額と生涯(保有残高)の利用上限額が決められています。(この2種類を併用する事が可能です。)
年間の利用上限額は「成長投資枠」は240万円まで、「つみたて投資枠」は120万円までです。また生涯(保有残高)の利用上限額は「成長投資枠」は1200万円、「つみたて投資枠」と合計した保有残高は1800万円までと決められています。いずれも買付代金を基準に加算され、既に買付けた商品を売却した場合はその翌年の保有残高から売却分が差し引かれます。
尚、 「成長投資枠」と「つみたて投資枠」では、購入可能な商品が異なりますので、注意が必要です。
- NISAでは非課税上限額以外に購入可能な金融商品の制限はありますか?
-
NISAは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つから構成されており、「成長投資枠」では、上場株式や投資信託を幅広く購入する事ができますが、「つみたて投資枠」は、毎月積立ができる投資信託のうち、買付手数料が無料などの条件をクリアした商品だけが買付できる制度になっています。
取引について
- 株式投資は何歳からできますか?未成年でも株は買えますか?
- 株式投資に年齢制限はありません。未成年者でも投資をできますが、その際には親権者(両親)の同意確認が必要になります。
- 株の取引をしている時間帯を教えてください。
- 日本国内の上場株式は、ほとんどが東京証券取引所(東証)で取引されています。東証では、9:00~11:30(前場)と12:30~15:30(後場)が取引時間となります。
- 株の値動きは毎日見守らないといけませんか?仕事や子育てに忙しく、株価を確認する時間が取れません。
- 例えば配当や株主優待を期待した銘柄を中長期に保有する投資スタンスであれば、日々の株価の変動をあまり意識する必要はありません。また投資信託であればマーケット動向の判断はプロの運用担当者に任せる形になりますので、有効な選択肢になります。
また、急激な株価変動時には、お客様の投資目的に合わせたタイミングで当社からもご連絡いたします。その他ご不明な点等ありましたら、営業社員にお問い合わせください。
- ネット証券で株を始めたのですが、投資の仕組みがよくわからず、取引を止めてしまい ました。株のチャートの読み方など初歩的な質問をしてもいいですか?
- どんな質問でも遠慮せずにお寄せください。ご質問の株価チャートとは、過去の株価と売買された量をグラフ化したもので、株の銘柄選別の際に将来の株価予想によく利用されます。ただし、チャートはあくまでも過去の株価の推移であり、将来を約束するものではありません。詳しくは当社営業社員にお問い合わせください。
- 対面販売だと投資のアドバイスが聞けて心強い反面、強引に勧誘されないか心配です。
- 当社の営業社員は「お客様本位」の接客をいたします。無理な勧誘はいたしませんのでご安心ください。
- 有価証券投資にかかるコスト(手数料)はいくらですか?何度も売買すると損をしませんか?
-
手数料は金融商品ごとに売買金額をもとに設定されています。
なお、当社ではしん手数料サービスとして、全てのお客様を対象に投資信託の買付手数料を一律1.1%(税込み)としております。
また、50歳未満のお客様を対象に国内上場株式等の買い手数料を無料としております。(2022年7月1日より)
詳しくは当社HPのリスク・手数料等の説明、およびしん手数料サービス、取り扱い商品の各ページでご確認下さい。
- 証券取引を始めるのに、銀行口座は必要ですか?
- 金融商品の売買を行うにあたり、買付代金の入金や売却代金の振込みにはご自身の銀行口座を指定して頂く必要があります。また積立投信などで毎月一定額を購入する場合は、お客様の銀行口座から自動引落し(口座振替)する便利なサービスも利用可能です。
制度(証券税制)について
- 株にかかる税金について教えてください。確定申告の手続きは必要ですか?
-
株にかかる税金には譲渡益税と配当課税があります。証券総合口座(一般口座)ではお客様ご自身で確定申告をしていただく必要がありますが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は、確定申告が不要です(複数社での取引のある場合は除く)。
- 証券口座の種類を教えてください。
-
証券取引を行う為には、証券総合口座を開設する必要があります。証券取引を行う場合、通常、株式や投資信託の売買による利益に対して譲渡益税(配当金・分配金に対しては配当課税)がかかります。この税制上の取り扱いの違いにより、証券総合口座の中に、①譲渡益税を確定申告する「一般口座」、②譲渡益を損益通算できる「特定口座(源泉徴収あり・なしを選択)」、③譲渡益税が一定の金額まで非課税となる「NISA口座」の3種類があります。詳しくは当社営業社員にお問い合わせください。
- 特定口座について教えてください
-
株式や投資信託の売買による利益にはその20%が譲渡益税(配当金・分配金に対しては配当額の20%が配当課税)として徴収されます。通常の一般口座では損失が発生した取引は無税ですが、この損失分を他の取引で出た利益と相殺できるのが「特定口座」の損益通算です。1年間(暦年)のトータルの損益で譲渡益税が徴収されます。また年間のトータルが損失になった場合は確定申告によりその損失を3年間繰越す事ができます。尚、取引金融機関が複数社にまたがる場合は取引金融機関を跨いだ損益通算には確定申告が必要です。